
田中章滋(たなかしょうじ)
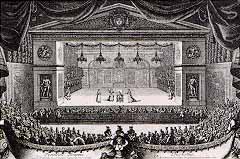
いい加減な都市計画や政権の交代などでよく起きる事だが、旧市街と新市街の間には時々不可解な街区が出現する。こうした街の外観は、壮麗(そうれい)な街の中心地の観(み)てくれが、末端では竜頭蛇尾(りゅうとうだび)に終わり、いかにも辻褄(つじつま)をあわせる仕方で、無計画な混乱と整序が同居しているものである。それは廃虚や、間抜けたように出来た空き地を廻(めぐ)って、路(みち)だけが整えられたりするからだろうか。放射状に伸びる路は、ローマか海でなければ一体何処(どこ)で終わればいいのか?といった設問に、結論を下すかのように、大概(たいがい)途中で断ち切られている。
そこはひと気が無く、如何なる時代からも取り残された、宛(さなが)ら「カリガリ博士」の撮影セットを思わせる奇妙な交差点だった。坂道が落ち合う五差賂一杯に、何の機能も果たさないと思われる縞(ストライプ)模様が覆い尽くし、まるで裏返った鬼ヒトデのようだった。その星型の東南の位置に、海洋レストラン「フェルマータ」はあった。店先には巨大な水槽が設(しつら)えられており、白黒のタイルがアールデコ調に装飾された店構えは、カレーやスズキやキンメダイの遊泳によって、さながらポンペイ遺跡のモザイクタイルを彷佛(ほうふつ)とさせる。
先程から私は、この水槽の前で、ガラス越しに映る反射を通して左右反転した街の鏡像と、海の生物達を交互に眺めている。そこには勿論、私自身の姿も投影されていて、同時に三つの視覚を愉しんでいた訳だ。
水槽の中の仮初(かりそ)めの海には、ホンダワラや珊瑚岩(さんごいわ)なども配されて、決して調理目的のみでない趣向が施されていた。しかし、私が最も注目したのは、豹紋蛸(ヒョウモンダコ)の存在だった。この恐ろしくも美しいこの海のピグミー族は、紫色と白の鮮やかな縹模様(はなだもよう)で人を魅するのだが、この蛸にうっかり刺されようものなら猛毒によって命を落とすこともあり得るのだ。こんな小さな蛸が、海の怪獣クラーケンや邪悪の権化であるマルドロールの蛸にも比すべき、猛毒を持っているとは、正に驚嘆に値する。
豹紋蛸は先程から揺らめく海藻の枝を、八本の足を器用に搦(から)めながら伝い歩きしている。すっかり蛸の観察に気を取られていた私の後方と思しき反射像に、その時、何か人影らしきものが過(よぎ)るのが、眼の端(はし)に飛び込んできた。
振り返らずに、視線のみをそちらに転じると、その人影は向かいの煙草屋(たばこや)の死角から現れたのであった。その歩みは余りにもゆっくりで、ゼンマイ仕掛けの人形のようにしか映らなかったが、仔細(しさい)に眺めるとそれは眼にオペラグラスを逆さに固定した男で、幽霊のように両手を前に翳(かざ)し広場を横断しつつあった。どうやら遠近感がまったく掴めぬらしい。
私の興味は、俄然(がぜん)この不可解な男の方へと奪われてしまった。男は初老で、蜘蛛(くも)のように痩せぎすの体躯(たいく)の上に長い頭を乗せていた。明らかにセム系の人種と窺(うかが)われる。が、印象はH・G・ウェルズ描くところの火星人に最も近かった。服装はスラックスに長首のセーターといった、いたってシンプルな装いで、矢張り奇異な印象の中心は、第一次大戦で頭部を負傷したアポリネールがつけていたハーネスと暗視鏡のような双眼鏡(ぐらす)であった。ここでは仮に彼の名をミロスと呼んでおこう。ミロスは煙草屋の角から何とか北側の床屋の角まで渡りきり、回転する有平棒(あるへいぼう)に眼を回したのか、激しく尻餅(しりもち)をついていた。
周囲には、彼と私以外誰もいないようだ。助け起こしに行かねば、そう思い、仕方なく急いで道を横切って、抱え起こしたミロスの体はまるで中身がないかのように、異様に軽かった。半開きの口元に耳を近づけると呼吸は淺く、両目をグラスで覆われているため、顔の表情はつかめない。どうやら意識を失いかけているようだ。ぐったりとしたその体をもてあまし、ぐるりと周囲をうかがってみたが、相変わらずひと気は断えたままである。ただ、巨大な水槽の中から豹紋蛸が、瞼のない目でじっとこちらを見詰めるばかり。
一瞬の躊躇(ちゅうちょ)の後、私はミロスの両目からグラスを取り上げた。彼は目を瞑(つむ)り低く呻(うめ)いただけで、たいした抵抗はしなかった。そのまま力無く横たわるミロスを地面に残して、私はグラスを自分の両目に当てて立ち上がった。一瞬、世界がぐらっと揺れた。確かにそう感じたが、あるいは気のせいだったかもしれない。
視界に映る光景は激変していた。波打つごときストライプ模様が視野一杯に広がり、それは地平線の果てまでも永遠に続くかと思われた。巨大な水槽があるはずの方向に視線を転じても、見えるのはただ茫漠(ぼうばく)と続くストライプ模様の海だけだ。
試しに一歩前に足を踏み出してみる。途端に視界全体が波のように揺れざわめき、眩暈(めまい)に襲われたように瞼(まぶた)の奥がずきずきと疼(うづ)いた。だが、光景に変化はない。見渡すばかりのストライプ模様だ。
ふと気がついて、足下のミロスに目を向けた。はるか彼方に豆粒ほどの大きさでミロスは横たわっている。そろそろと腰をかがめていくと、スカイダイビングの急降下よろしくミロスの体がぐんぐんと迫り上がってくるように見える。その感覚もまた、私に激しい眩暈(めまい)を引き起こす。
目を瞑(つむ)って大きく頭(かぶり)を振り、深呼吸を一つしてから、水槽があると思われる方角へ歩みを進めた。足を一歩踏み出すごとに視界がざわざわと揺れて蠢(うごめ)き、遠く地平線の彼方に見覚えのある水槽の姿が、一瞬、ちらっと映ってはまたすばやく消えていった。まるで広大な砂漠の中に、浮かんでは消えるオアシスか蜃気楼のようなその姿を追い求めて、私はのろのろとした歩みを続けた。
実際、遠近感の定まらない世界を歩むには、途方もない時間がかかった。それとも、私の時間感覚までもが極端に変化してしまったものか。とにかく、かなりの努力と膨大な時間を使って、ようやく私は再び大型水槽の前に立ち戻った。
そう思ったのも束(つか)の間、私は水槽の中の魚と化していた。仔細は解らない。グラスを装着した時から視覚は既に魚眼に近くなっていたが、私は水槽飼育用の階段を昇りきり、落下したのに相違(そうい)ない。冷たい海水も呼吸の困難も私は恐れなかったが、脱出しようともがきながら戦慄(せんりつ)を禁じ得なかったのは、豹紋蛸の存在だった。否、もう既に噛まれてしまったのかも知れない。珊瑚岩に強(したた)かに頭を打ちつけていたので、衝撃が先走った。まして痛みは水の中では伝わりにくい。それどころか、最早、全身の感覚が麻痺しつつあるのだ。必死にもがきながら、切れ切れに見える混乱した視覚に、あのミロスの顔があった。水槽を上から覗き込む仕種が、暗いトンネル状の視覚の遥か彼方に見える。確信を持って言うが、その顔には眼球がなく、無気味な笑いが浮かんでいたのだった。
スポンサードリンク